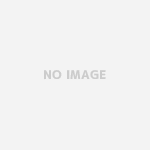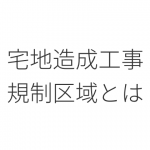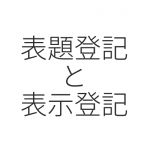公簿面積というのは、法務局で管理されている登記簿に記載されている土地の面積のことです。
土地の面積が知りたければ、法務局で「登記事項証明書」を取って、「地積」という項目を見て確認するのが一般的です。
登記事項証明書は、国の機関である法務局が管理している登記簿の内容、つまり不動産の情報を証明する公的な書類です。
公的な書類なのだから、そこに載っている情報も正しいはず・・・普通はそう思いますよね。
でも実際に土地の面積を測量してみると、「登記事項証明書の面積より大きい!」「登記事項証明書の面積より小さい!」といったことがあります。
公的機関で管理されている登記簿に基づき発行される書類なのに、どうしてこんなことが起こるのでしょうか。
それは、日本の税制の歴史と関係があります。
日本の納税~生産物(物納)から金銭(金納)へ
日本が、税を金銭で支払うようになったのは、明治時代になってからです。
それまで日本の税制は、古くから、田畑で収穫できる生産物の収穫量を現在でいう課税標準とし、耕作者が直接その生産物(米や作物)を納めるものでした。(他にも、布や塩、工芸品なども税として納めていましたが、ここでは触れません。)
田畑の生産物を直接納めるので、納める量にも地域差がありました。
これが、明治時代になって、田畑の生産物ではなく、全ての「土地」に課税し、土地の価値に見合った金銭を土地の所有者が納めるという、日本全国共通の課税制度に改められました。
そして新しい税制のために、土地の測量が行われ、現在の登記簿の前身となる地券台帳が作成され、その後制定された登記制度に引き継がれていくのですが、当時の測量技術が未熟だったこと、測量の専門家ではなく素人が測量していたこと、税を軽減を図るために故意に土地の面積を小さく申告したことなど、様々な要因の結果、その内容は必ずしも正確ではありませんでした。
よって、現在の登記簿においても、実際の地形や面積が現況と一致しない、といったことが起きているのです。
公簿面積と実測面積を合わせるには?
実際に測量した面積に登記簿を修正したいときは、「地積更正登記」を法務局に申請します。
ただし、この地積更正登記も、土地の分筆と同じく「境界が確定されていること」が必須条件です。
境界が確定されていないと、地積更正登記はできません。
また、現在、地方公共団体が主体となって、「地籍調査」が行われています。地籍調査は、土地の測量を行い境界の確定、権利関係を明確にして、法務局に備えられている登記簿や地図に、正確な情報を反映させる事業ですが、昭和26年から実施され既に半世紀以上が経過しているにも関わらず、なかなか進んでいないのが実情です。